| 容器包装リサイクル法について、環境省の担当の方に解説していただきました。 問1 容器包装リサイクル法(以下の問で「容リ法」という。)は、正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称とのことですが、リデュース、リユースに比しリサイクルが重視されているのですか? 例えば3R法と呼ばない理由はあるのですか? 答1 容器包装リサイクル法は、消費者には容器包装をゴミとして出す時に分別することをお願いし、市町村にはそれを分別して収集し、そして、容器包装を製造したり、販売時に利用する事業者にはそのリサイクルを義務付け、レジ袋やペットボトルなど私達が使用した容器包装を商品として再生するリサイクル(容器包装リサイクル法では「再商品化」といいます。)を進めることを目的に、平成7年に制定されました。 その後、循環型社会を構築するための基本法である循環型社会形成推進基本法において、廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルの順に優先的に取り組むといった「3Rの原則」が定められたことにより、今年6月に改正が行われた際には、新たにリデュース、リユースにより容器包装のゴミを減らすことが内容に加わりました。今後は私達みんなで容器包装のゴミを減らしていくことが重要となります。このように、法律名に変更はありませんが、現在は「容器包装の3R 法」と呼んでも差し支えない内容になっています。 問2 容リ法で規定する「容器」と「包装」とはなんですか?  答2 この法律でいう、容器とは飲み物を容れるペットボトル、缶、紙パック、ガラスびんや、買い物で使用するレジ袋、紙袋、段ボールなど、商品を容れる器をいいます。また、包装とはプレゼントの包装紙や刺身を容れたトレイにかかったフィルム(※トレイは容器になります。)など、商品を包むものをいいます。 この中には、カップラーメンの容器やふた、靴の空箱、ポケットティッシュを包む薄いプラスチックの袋なども含まれ、私たちの生活の中に数多く存在します。皆さんがよく利用する製品についているPET、プラ、紙、アルミ、スチールなどのマークがついている容器や包装は、容リ法でいう容器包装に該当します。 問3 容リ法では、第1条(目的)を見ても、地球温暖化防止については直接規定されていません。3Rと地球温暖化防止との関連は、どの様なものか、解説して下さい。 答3 一般的にゴミは、埋め立てるか、焼却することにより処分されます。容器包装も燃やすことにより地球温暖化の原因となる温暖化効果ガスが発生しますので、容器包装の3Rを進めることにより、本来はゴミとして燃やされていた容器包装をゴミとして出さず、またゴミとして出されたものをリサイクルすることにより、容器包装を燃やす量を少なくすることで温暖化防止にも役立っています。 また、い容器包装の削減は。環境省が温暖化効果ガスの排出削減のために国民運動として取り組んでいる「チームマイナス6%」の取組の一つでもあります。 問4 容リ法で消費者に3Rを求めることを直接規定した条文は、第4条(事業者及び消費者の責務)だけですか?第4条で、リデュースについて書かれているのは、どの部分ですか?また、リユースについて書かれているのは、どの部分ですか? 答4 消費者に3Rを求めることを直接規定した条文は第4条です。また、第4条におけるリデュースの規定は「容器包装の過剰な使用の抑制」が、リユースの規定は「繰り返して使用することが可能な容器包装の使用」が例示として規定されています。 なお、今回の法改正において、3Rの取組を促進するための取組が盛り込まれました。例えば、消費者の3Rに向けた意識の向上を図るため、環境大臣が※「容器包装廃案物排出抑制推進員」を委嘱し、意識啓発を行うこととしました(第7条の2)。また、事業者に対し例えばレジ袋の有料化など、消費者の協力も得ながら容器包装の3Rを進めるための取組を求めることにしました(第7条の4)。 問5 リデュースについて、 一般に発生抑制という言葉が使われますが、法律上これに対応する用語はどれですか?排出抑制という言葉がありますが、それとの関係を解説して下さい。 答5 容器包装リサイクル法においては「排出の抑制」という用語を用いていますが、これは容器包装のゴミが出ることを抑制するという意味であり、その方法としては、マイバッグの利用などによりそもそもゴミとなりうる容器包装の利用を控える「発生抑制」すなわちリデュースや繰り返し利用できるリユースカップを使用するなど「再使用」すなわちリユースを進めることにより、容器包装のゴミが出ることが抑制されることになります。このため、排出抑制と発生抑制の関係については、「排出抑制」の中に「発生抑制」が含まれます。 問6 今年6月の法改正で、衆参議院の附帯決議において「発生抑制を最も優先すべきであることを、…消費者等に徹底する」という趣旨の項目が盛り込まれましたが、容リ法でどう対応するのですか?(問3との関係で) 第4条で解釈できるのですか? 答6 容リ法ではこの法律に基づく取組の基本的方向を規定した基本方針が定められていますが、今後、この基本方針を改正し、例えば循環型社会形成推進基本法に定める「3Rの原則」に基づき取組を進めることを明記していきたいと考えています。 問7 リデュースを最優先するため、環境省が消費者に対して行う施策は何ですか? 答7 容器包装リサイクル法の改正を受け、環境大臣は、排出の抑制のための施策として、「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱することができることになりました。この推進員は容器包装廃棄物の排出の抑制のため、環境省・地方公共団体等の依頼に基づく講演、執筆等を通じた啓発、消費者のマイバッグ持参に関するキャンペーンやアンケート等の調査を行うことを予定しています。 また、環境省では事業者と行政との自主協定を推進することにより、リデユースに向けた自主的取組を行う事業者を普及させ、消費者がこうした事業者を利用できる機会を増加させたり、広報キャンペーンや環境教育などによって消費者の減量意識の向上を図るとともに、繰り返し使える容器(リターナブル容器といいます。)の地域での普及や地域通貨を活用した取組を支援することで、容器包装の3Rを推進することとしています。 問8 リデュースを最優先するため、環境省としては、消費者には何をどのようにしてほしいとお考えですか? 答8 容器包装のゴミを減らすことは、私達の日常生活における様々な工夫により進めることができます。 例えば、買い物に行く時はマイバッグを持参することによリレジ袋や紙袋の使用を減らすことが可能です。包紙が省略されているなど簡易包装がなされた商品やシャンプーなど詰め替え可能な商品を買うことも容器包装のゴミの減量化につながります。さらに、タンブラーなどリユースカップを持参することも効果があります。 最近は、このような容器包装の減量に向けた取組にインセンティブを与えるケースも増えており、レジ袋を控えた際のポイントや、タンブラー持参による割引を行っているお店もあります。こうしたインセンティブを活用することにより、マイバッグの利用などによる容器包装のリデュースに一層取り組むことも期待しています。 このような生活に身近なところで出来る取組を是非実践し、またその取組の環が家族や会社、学校等に広がっていけば、容器包装のゴミは確実に減っていくと思います。 (参考) 容器包装リサイクル法の概要 1 容器包装リサイクル法の制定の背景と内容 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下、「容器包装リサイクル法」といいます。)は、家庭等から排出される一般廃棄物の最終処分場(埋立処分場)が残りわずか8.5年分(平成7年当時)しかないというひっ追等の問題に対し、一般廃棄物の中で、容積比で6割という大きな割合を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装のリサイクル制度を構築し、一般廃棄物の最終処分場へのフローの減量を効果的に図ることを目的として、平成7年6月に制定されました。 容器包装リサイクル法は、一般廃棄物について、市町村が全面的に処理責任を担うという従来の考え方を改め、容器包装の利用事業者や容器の製造等事業者、消費者等にも一定の役割を担わせることとしました。 具体的には、家庭から排出されるスチール缶、アルミ缶、ガラスびん、段ボール、紙パック、紙袋等の紙製容器包装、ペットボトル及びレジ袋等、のプラスチック製容器包装の8種類について、消費者の協力を得ながら市町村において分別収集を実施することとし、容器包装の利用事業者(飲料メーカー、スーパー等の小売業者等)及び製造事業者(容器メーカー等)は、市町村によって収集された容器包装廃棄物を、個々の事業者が負担すべき量に応じて原料化や素材化等の再商品化(リサイクル)を行うこととされました。実際には、事業者は自ら再商品化を行うほか、自ら再商品化を行うことが困難な場合もあるため、容器包装リサイクル法に基づく指定法人(平成18年9月現在の指定法人:財団法人日本容器包装リサイクル協会)に再商品化を委託することによって、再商品化義務を履行することとなります。 2 容器包装リサイクル法の成果と課題 (1)容器包装リサイクル法の成果 容器包装リサイクル法の施行から10年が経過しましたが、その間分別収集を実施する市町村の増加に伴い、分別収集量が着実に増加しました。その結果、一般廃棄物の最終処分量についても年々減少するとともに、最終処分場の残余年数も一定の改善が見られているなど一定の成果が得られました。 (2)容器包装リサイクル制度の課題 しかしながら、いくつか課題もあります。まず、容器包装リサイクル法制定当時に課題とされた最終処分場のひっ追という問題が依然として残っていることです。一般廃棄物の最終処分量は減少しているものの、平成16年における最終処分場の残余年数は13.2年であり、最終処分場の確保が難しくなっている中では、安心できる状況にはありません。 さらに、容器包装リサイクルにかかる社会コストの増加という問題も生じています。市町村による分別収集・選別保管コストは約3,000億円で、ごみ処理量の減少による焼却・埋立て費用の削減分を差し引いた容器包装リサイクル法施行後の純増分は約380億円(いずれも環境省による平成15年度の推計)となっています。 3 容器包装リサイクル法の改正 こうした課題に対応するため、政府は、大学の教授、民間企業の専門家、非営利団体の代表等の有識者からなる審議会を数十回にわたって開き、容器包装リサイクル法の制度の見直しの検討を行ってきました。検討結果をまとめた意見具申においては、上記のような評価と課題を踏まえ、我が国における3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進を通じて、天然資源の消費を抑制し、環境ヘの負荷ができる限り低減される循環型社会の構築を更に推進するため、次のような基本的方向に沿って、容器包装リサイクル制度の見直しを行うことが提言されました。 ①循環型社会形成推進基本法における3R推進の基本原則に則った循環型社会構築の推進 循環型社会形成推進基本法に規定された基本原則に基づき、リサイクルより優先されるべき発生抑制(リデュース)、再使用(リサイクル)を更に推進する。 また、リサイクルについては、国内のリサイクル産業の健全な発展を視野に入れて、効率的・効果的な推進を図る。 ②国・地方自治体・事業者・国民・NPO等すべての関係者の協働 容器包装廃棄物に係る3Rの推進に係る国・地方自治体・事業者・国民・NPO等の各主体が、自らが率先してできる限りの取組を推進すると同時に、相互連携による積極的な対応を目指す。 ③社会全体のコストの低減 深刻化する国及び地方自治体の財政状況、厳しさを増す経済情勢等にかんがみ、循環型社会の構築等に係る効果とのバランスを常に考慮しつつ、容器包装廃棄物に係る3Rの推進のための社会全体のコストを可能な限り低減させる。 政府は、この意見具申を踏まえて改正リサイクル法の法律案をまとめ、国会に提出しました。その後、国会での審議を経て、本年6月に改正リサイクル法が成立しました。その概要は以下のとおりです。 4 改正リサイクル法の概要 (1)排出抑制に向けた取組の促進 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進し、一般廃棄物の最終処分場のひっ迫という問題を解消するため、排出抑制に向けた基本的な方向を国として示した上で、消費者の意識向上を図るとともに、消費者における排出の抑制を促進するための事業者(小売業者)の取組を促進するため、以下の改正が行われました。 ①目的・基本方針等における排出抑制の促進に係る規定の追加 容器包装廃棄物の排出抑制を促進することを明確にするため、法の目的規定、基本方針に定めるべき項目の規定、国及び地方公共団体の責務規定等に、排出抑制の促進に係る規定が追加されました。 ②消費者の意識向上・事業者との連携を図るための取組 容器包装廃棄物の排出の抑制についての消費者の意識啓発等を図るため、環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱することとしました。この推進員には、例えば、事業者によるレジ袋の有料化等の措置と消費者によるマイバッグの持参等、両者の連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発することや、消費者の容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査及び当該調査に基づく取組を促進するための指導・助言等といった活動を担っていただくことが期待されます。 ③事業者の自主的取組を促進するための措置 ⅰ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための事業者の具体的な取組については事業者によって知見や意識に差があり、現状においては取組の進度にばらつきが見られます。 このため、容器包装利用事業者(小売業者)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために取り組むべき措置に関する「判断の基準となるべき事項」(判断基準)、を主務大臣(事業所管大臣)が定め事業者による容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を一層推進することとしました。 ⅱ 主務大臣は判断基準に基づき、事業者に対する指導・助言を行うとともに、容器包装を多量に利用する事業者に対し、事業活動に伴う容器包装の使用量及び容器包装の使用の合理化のために取り組んだ措置の実施状況に係る定期報告を義務付けることとしました。 ⅲ 判断の基準に照らして取組が著しく不十分な容器包装を多量に利用する事業者に対しては、勧告・公表・命令の措置を講ずることとし、この命令違反に対しての罰則(50万以下の罰金)を設けることとしました。 ④ 市町村分別収集計画の公表の義務付け 容器包装廃棄物の分別収集・排出抑制等に係る事業者・消費者の理解を深め、事業者、消費者、地方公共団体等の協働による取組を促進するため、都道府県による都道府県分別収集促進計画を策定した場合と同様、市町村は市町村分別収集計画を定めたときは、これを公表するものとしました。 (2)事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設 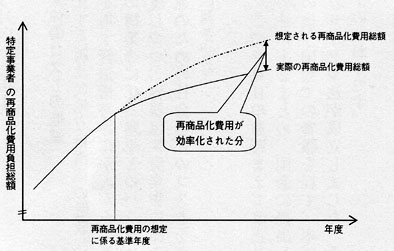 市町村が質の高い分別収集(果物の除去、消費者への適正な分別排出の徹底等)を実施した場合、再商品化の質の向上等により処理コストが低減され、実際の再商品化費用が当初想定していた再商品化費用を下回ることとなります。 このため、市町村による分別収集の質を高め、再商品化の質的向上を促進するとともに、容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの抑制を図るため、実際に要した再商品化費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集による再商品化の合理化への寄与の程度を勘案して、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設することとしました。 なお、各市町村への資金の拠出については、より効果的・効率的に容器包装に係る3Rを推進する観点から、市町村ごとの分別基準適合物の質やこれによる再商品化費用の低減額に着目して行うことが考えられます。 5 その他の制度改正 これらの改正のほか、再商品化義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない、いわゆる「ただ乗り事業者」が一定数存在していることから、今回の法律改正で義務違反の罰金の額が50万円から100万円に引き上げられました。このほか、事業者への理解を求めるための説明会等の普及啓発を実施する予定です。 また、自ら定めた計画どおりに容器包装廃棄物を事業者に引き渡さない市町村があり、分別収集された使用済ペットボトルが海外に輸出されることにより、国内の安定的な再商品化に支障が生じるおそれがあります。このようなペツトボトル等の海外への輸出については、市町村に対して自ら定めた計画に従って容器包装廃棄物を事業者に円滑に引き渡すことを求める予定です。さらに、市町村による再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理を促進するため、市町村により分別収集された容器包装廃棄物の処理の状況を適切に把握することや、市町村に対する情報提供を行っていく予定です。 |